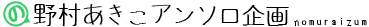眠らない女王様とジャックの憂鬱
「浅見はさ」
昼休みの屋上。
暖房の効いた校内からやってくると冷気が頬に嬉しいこの場所で、突然話を切り出しながらストローに口をつけたのは時緒だった。
やっと肩まで伸びた髪を揺らして、この一杯が美味い、みたいな表情をする。
「何」
何気なく返事をして、ストローを吸う。
「碧さんをどうやって起こしてる?」
「……っ! ……はあ?」
思わず喉に詰まらせかけたジュースをなんとか飲み下す。
「突然何を……」
「いや、なんとなく」
何となくでそんな唐突な質問をぶつけてきたのかコイツは。
「じゃあ、おまえは清宮さんをどうやって起こしてるの?」
「え。とりあえずスタンダードに揺すったり、声かけたり――でもなかなか起きない訳ですよ。じゃあもっとインパクトのある起こし方、ってやってたら、起きた瞬間ビンタとかパンチとかが」
「……」
容易に想像がついたその様子に、思わず溜息をつく。その隣で時緒は「もうルームメイト生活だって三ヶ月も絶つのに里花ちゃんったら……!」なんて言いながら、いやいやと頬に手を当てて嘆いていた。
「経つ、な。終わってるのかおまえのルームメイト生活は」
何となく指摘すると、時緒はけろっとした顔で「そんなことないですヨ?」と女子のような顔で頷いた。が、そこは無視した。
「話がずれたが……それはおまえが悪いんじゃない?」
「えー。ワタシは里花ちゃんが寝坊したりしちゃいけないって思ってるだけですよ?」
「じゃあ、起こし方が悪い」
それにしても、とストローを吸うと、ぺこん、と小さな音がした。
「清宮さんも警戒心が薄いねえ」
「いやいや。そこはおれが信頼されてるって言って欲しいよ」
はいはい、と適当な相槌を打つと、時緒は「それで」と放り投げた話を投げ直してきた。
「どうなのよ?」
「どうもこうも……」
「こうも?」
「……」
考える。
オレは、碧を起こした事があっただろうか?
これまでのルームメイト生活を考える。
考える。
「……おーい、あさみー?」
「――無い」
「は?」
時緒の方へ顔を向けて、告げる。
「オレは碧を起こした事が無い。あったとしても、多分、片手で足りる」
ぽかん、とした表情の時緒の瞳に、難しい顔をした自分がちらりと見えた。
「そもそも、あの部屋で寝てる碧を知らないかもしれない……」
→ Chapter 1 →
昼間の疑問は思った以上に尾を引いていた。
部屋に戻っても頭を離れず、考えてしまう。
この生活を始めて随分と経つ。
だというのにオレは、碧がこの部屋のベッドで寝ている姿というものを思い出せないでいた。
彼女の寝顔を知らない、という訳ではない。
そんなの小さい頃から何度も見てきた。小さい頃に起きた、虫干しの騒動以来、一緒に寝る機会なんて山ほどあった。年末の騒動の時、地下倉庫で見たあの表情は寝顔と分類しても良いはずだ。
……多分。
でも、それ以外。特にこの部屋では?
――。
想像はつくが、どれもコレも現実味が無い。
ただの空想。悪くて妄想。
そう言い切れる位に実感が無い。
つまるところ。さっぱり思い出せなかった。
「……無いな」
「何が?」
「!?」
がた、と思わず椅子が揺れた。
いつの間にか帰ってきていたらしい碧が、ひょこりとこちらを覗き込んでいた。
「え、いや……別に」
なにも、と思わず言葉がしどろもどろに零れる。
「なにか悪い事考えているのかしら?」
「いやいやいやいや」
す、っと何処からとも無く取り出されたハリセンに、少しだけ背もたれへと後ずさる。
考えているなら容赦なくそのハリセンで叩き潰す気だ。
普段の柔らかな物腰とは異なる威圧感には、誰もが正直に答える事を選ぶだろう。
オレだってそうする。
ぶんぶんと首を横に振り、ついでに両手を上げて否定する。と、真偽を確かめるようにじっと見つめてきた。
椅子の上で逃げ場も無く、両手上げて降参ポーズのオレと、ハリセンを両手でそっと構えて見下ろす碧。
絡む視線が緊張の糸を引く。
疑うような、疑問そうな。そんな目は、少しだけ清宮さんが時緒に向けていた疑惑の目に似ている。
寮で寄ってくる女子は笑顔であることが殆どだ。少し前の清宮さんみたいに、一部は少し怯えたような顔をする。だが、誰もこんな目でオレを見ることはない。
女子とは皆、こんな目を持っているのだろうか。
だとするならかなり恐ろしい存在だ。
そんな事を思いながら、どれだけの時間が経ったのか。――あるいは一瞬だったのかもしれないが。碧は何も無いと判断したのか、そう、と呟いて身を引いた。
「それなら良いんだけど。ダメよ? 時緒くんや里花ちゃんを困らせるような事しちゃ」
「しないしない」
懸命の否定が通じたのか、彼女はようやくハリセンを下ろしてくれた。
それに安堵の息を吐く。
「でも、浅見が隠し事だなんて久しぶりね」
「え。そう、か?」
その答えに彼女はぱちりと瞬きをして、不思議そうな表情をした。
「やっぱり何か隠してたの?」
「――っ!?」
やられた。
しまった、と口を押さえて更に逃げられない事をしたと気付く。
だが、時は既に遅い。
ハリセンの一撃を思わず覚悟して身構える。
――が、その一撃はいつまで経っても来ない。
腕の間からそっと目を覗かせると、彼女はさっきと同じポーズのまま、オレを見上げていた。
「――ふふ」
碧は口に手を当て、くすくすと笑う。
そろりと構えを解くと、彼女はハリセンを握ったまま背中に腕を回す。
「別に、浅見がわたしに隠し事をするのがいけない、なんて言わないわ。だって、その位ヤンチャな方がいいもの」
「……そうですか」
そうよ、と彼女は深く頷く。
「浅見はそんなに大きいんだから、それくらいかわいげがあった方が良いわ」
「……」
はいはい大きく育って悪かったですね、と思わず溜息が漏れた。
→ Chapter 2 →
――ふと、目を覚ました。
いつの間にか寝返りを打ったのか、目の前は壁。
明かりの無い部屋は、薄暗い割に細かな所までよく見える。
だが。時計を見るまでもなく、まだ夜は深い。
これは単に、暗闇に目が慣れているからそう見えるだけだ。
どうやら妙な時間に目を覚ましてしまったらしい。
珍しい事もある。
このまま目を閉じれば、すぐにでも眠りにつけるだろう。と再度寝返りをうつと、部屋の反対側の景色が目に入った。
壁に向かっていた時より、何倍もの奥行き。
その、更に奥。
「――」
テーブルを挟んでそこにあるのは、ルームメイトのベッド。
オレの記憶の中でそれは、常にホテルのように整えられている。
だが、今は違った。
ベッドの上に横たわる人影。寝ているのは勿論、碧だ。
彼女は寝たばかりなのか、寝返りを打っていないだけなのかは分からないが、仰向けで静かに寝息を立てている。
眠っているその横顔は、暗い中でも分かる程穏やかで。普段ハリセンを振り回しているようにはちっとも見えない。
碧の寝ている姿。
夜中に起きる事が初めてではないが、昼間のあの疑問のせいか、何となく意識が離れない。
寝る前の事を思い出す。
夕飯を食べて、部屋に戻って。
風呂に行って。戻ってきても、彼女は起きていた。
いつの頃からか使っているトランプ柄の栞を横に置いて、本を読んでいた。何を読んでいるのかは分からない。ページを捲る速度はそんなに速くない。ぺらり、と紙がこすれて捲られていく音が、時々部屋に響く。
よくある光景だ。
ただ、今日だけは。テーブルに置かれた赤いトランプの視線が、丁度オレの方を向いているように見えた。
――ハートのジャック。
いつだったかも、誰が言ったかも忘れたけど。そのモデルはジャンヌ・ダルクの戦友だと聞いた事を思い出した。
彼女の隣で共に戦ったその心境は、どんなものだったのだろう?
ルームメイトとして。仲間として。共に危機をくぐり抜けてきたオレには、少しくらい分かるだろうか?
そもそも。
オレはそれだけの役割を、果たせていただろうか?
彼女の隣で。共に。時には助け、戦えたんだろうか?
なんて。
ハートのジャックを重ねてみた所で、そんなのただのお伽話だ。
ついでに考えるなら。彼女はクラブのクイーンで良い。
混紡の代わりにハリセンを持った、女王様。
うん、お似合いだ。
そんな事を考えながら見つめ合う、ハートのジャックとオレ。
トランプは何も言わない。答えをくれる訳でも無い。
なんだか一人で気まずくなってきた。
紛らわすように髪を乱暴に拭き、目を逸らそうとした瞬間、碧が顔を上げた。
「どうしたの? そんな所でいつまでも突っ立っちゃって」
湯冷めしちゃうわよ、なんていいながら首を傾げる。
「あー……うん。なんでも、ない」
自分でも分かるほどに、歯切れの悪い返事だが、碧は「そう」とだけ答えて小説へと視線を戻した。
「というか」
「?」
「碧は、まだ起きてたのか」
つい、そんな事を言った。
思わず口を突いて出た一言に、彼女は「あら」と当たり前のような顔で言った。
「わたしはいつも起きてる時間よ?」
碧は一体何時に寝て、何時に起きているのか?
夜は。
いつも机に向かっていた。
それは課題だったり、予習復習だったり、時には読書だったり。
だが。確かに碧は起きていた。
うたた寝をしている事もあったようだが、ドアを開ける音で必ず目を覚ます。
朝は。
オレが起きる頃には身支度を整え終えている事が多い。
ハリセンで叩き起こされる事も、ある。
そんな日々。
思い返さなくても。
それが、この部屋の日常風景だった。
オレは。
彼女が布団に入る姿も、起きる姿も。やっぱり知らなかった。
→ Chapter 3 →
碧はいつも、オレより遅く寝て、早く起きている。
それは単なる生活習慣の違いだと思っていた。
幼い頃とは違う。少し離れただけで変わるものだってあるから、その一つだろうと思っていた。
闇が燻る部屋の中。ベッドに横になったままで考える。
「でも……違うのか?」
「――何が?」
跳ね起きた。
「な……ちょ……え!?」
ぱくぱくと口は動くが、声がうまく出ない。
そんなオレの様子など気にかけた様子も無く、彼女も起き上がる。
「浅見。夜中に騒ぐと迷惑よ?」
誰のせいだと、という言葉も空回りさせて、オレはようやく大きく息をついた。
「起きてるなら起きてるって言ってくれ……」
「あら。先に起きたのは浅見じゃない」
そうでしたか、とついた息は、ひやりとした空気に沈んだ。
薄暗い部屋では、表情もぼんやりとしか見えない。
月の明かりもない、闇に慣れた目だけが頼りの部屋で二人、それぞれのベッドに座して向かい合う。
「こうやって部屋の電気消して二人とも起きてるなんて、なんだか昔みたいね」
「人数は半分だけどな」
そうね、と彼女は笑いながら小さく頷き。
「それで」
と、言葉を繋いだ。
「浅見は一体何を悩んでいるのかしら?」
どきっとした。
一体いつからバレていた? と思わず過去の自分を思い返す。
もしかしたら、最初からかもしれない。
碧の観察眼を甘く見てはいけない。
そういうものだ。と観念して、正直に答える事にした。
「いや、おまえ一体いつ寝てるのかなって」
「あら、そんな事気にしていたの?」
「うん、まあ……」
歯切れが悪くなった答えに、彼女はそうね、と少し考えて。
「浅見が寝た後から、起きる前ね」
分かりきった答えが返ってきた。
「――なんで?」
目が慣れた暗い部屋とお互いの距離が、その疑問を押し出した。
なぜ、オレの寝る時間を意識してずらしているのか。
そして、答えもすぐに返ってきた。
「だって、寝姿って無防備でしょう? 変な事されたらいけないと思って」
警戒。
それが答えらしい。
それは、普段から彼女が事ある毎に口にしているもので。
当たり前と言えば当たり前すぎる解答。
その対象はオレも例外ではなかった。それだけの話。
だけど。なんだかその言葉はずしりときた。
心のどこかで、少しは思っていた。
幼なじみだから。気心なんてとっくに知れた仲だから。
好き嫌いも。得意な教科も。ハリセンを武器として振り回して、女王様さながらの威厳を持っている事も。オレの特技も。
それだけお互いを知る仲だ。
オレと葵、それから時緒。
せめてこの三人だけは、例外に当たると。
どこかで信じていたのかもしれない。
思わず力が抜けた。
「碧はオレを何だと思ってんだよ……」
溜息に混ぜて被せたその言葉に彼女は首を傾げたらしい。さらっと髪の流れる音がする。
「浅見は浅見よ? かわいかった幼なじみ」
最近はすっかりかわいくなくなっちゃったけど、と溜息をつく。
「……はあ」
「でも」
「でも?」
「浅見は、男の子だもの」
ふふ、と小さく笑って彼女は続ける。
「男ってヤバンなものでしょう?」
「それをオレに言うのね……」
でも、否定は出来ない。
それは、彼女の口癖であり。
この部屋の事情であり。
オレの感情だ。
そーですね、と溜息に混ぜて小さく呟くと、沈黙が降りた。
だが、碧が動く気配はない。
「――じゃあさ」
思わず、問いが零れた。
「おまえも他の生徒と同じ部屋が良かったか?」
「浅見?」
「……あ、いや」
自分が何を言ったか。いや、言いかけたのかを認識して、慌てて誤魔化すが、遅い。
気付いた時には、既に相手の手元にしっかりとキャッチされ、投げ返された。
「浅見は嫌だったの?」
「いや、そう言う訳じゃ―― ! ない……ないんだ」
咄嗟に出た否定の言葉は、途中で失速して床に転がった。
まだ。まだ言う訳にはいかなかった。
暗いのに、表情が読まれていそうで思わず顔をそらす。
そもそも。彼女と同室にしてくれという「条件」を若君に出したはオレだ。
碧なら正体がいつバレるかと怯えなくてもいい。ルームメイトには情報の開示と協力の要請は必要だろうが、それも必要ない。
なにより。
幼い頃から一緒で、信頼できると分かりきっている相手。
慎重な彼女なら安心だろうが、万が一危ない事に巻き込まれても一番に気付ける距離。
嫌である理由は、無い。
……なんて言い訳を手持ちのカードに並べ立てていると、余計な事まで喋りそうになる。結局濁したまま転がった言葉に気まずさを感じていると、「浅見」と小さく呼びかけられた。
「わたしは、この部屋で良かったと思ってるわよ?」
返ってきたのは、穏やかな声だった。
だって、と彼女は少しだけ声に力を込める。
「わたし、スパイであるのは構わないけれども、女の子の部屋に盗聴器やカメラを仕掛けたりしたくないわ。プライバシーは大事だもの」
「……え?」
どういうことですか? と思わず聞きたくなったが、彼女はそんな事しなくても答えをくれた。
「浅見みたいなサギ師が他の女の子と一緒だなんて、何が起きるか分からなくて心配だから」
「カギ師な。ってか、オレのプライバシーは良いんですか……」
「小さい頃から一緒だったもの。少し位なら減らないでしょう?」
いや……気付いたら減りそうだと思う。何かは分からないけど。
マイペースなその解答にすっかり乗せられている事に気付いて、思わず渋い表情になった。
そんな変化に気付くこと無く、碧の話は続く。
「本当は時緒くんのルームメイト選びも心配だったの」
葵くんがルームメイトでも良かったのだけど。なんて怖い事もさらっと言い足す。
「でも、里花ちゃんなら大丈夫。わたしたちが卒業しても、仲良くやってくれるわ」
それに、と彼女は続ける。
「時緒くんならきっと、里花ちゃんを困らせたり悲しませたり。そんな事しないわ。浅見だってそうでしょう?」
「……? 清宮さんを?」
「“ルームメイト”を、よ」
「……ああ」
なるほど、と頷く。
「それは、勿論」
答えに迷いは無い。
すると彼女の小さな笑い声が聞こえた。
「うん。浅見ならそう言うって分かってた。浅見は優しいし、面倒見だって良いもの。いざって時はちゃんと来てくれるでしょう? だから、浅見と同じ部屋で良かったと思うの」
そのふわっとした声。
表情は見ていないがきっと、穏やかで花が零れるような微笑みだろう。
そんな気がした。
□ ■ □
「あら。もうこんな時間」
碧がそんな声をあげた。
「え、今何時?」
「三時くらいよ」
その言葉と同時に、ごそ、と布団に潜る音がした。
「ほら、浅見も寝ないと寝坊しちゃうわ」
ん、と頷いて自分も枕に頭を預ける。
「――あのな、碧」
「なあに?」
「うん……オレの事はさ、気にせず寝てくれ」
別に何も心配する事はないから、と言葉に含める。
それで頷いてくれるとは思っていないが、言っておかなくては気が済まなかった。
この学園に来て今まで頑張ってきたんだ、後少しくらいの辛抱。
きっと、どうってことない。
その言葉に彼女は小さく笑った。
「そうね……でも、コレもわたしの楽しみのひとつなの」
「え?」
聞き返したが、それ以上の答えは無かった。
→ Epilogue →
朝。
目を覚ますと、隣のベッドは綺麗に整えられていた。
カーテンは開けられていて、部屋はとても明るい。
部屋には誰も居ない。きっと髪でも結いに行っているのだろう。
壁のカレンダーはとうに春を示しているが、部屋の空気はまだまだ寒い。
そんな冷えきった空気の中で、さっさと身支度を整える。
髪をとかしながら、また少し伸びたな、と思う。
邪魔臭いと思っていたこの髪も、もう少しの辛抱だと思うとなんか感慨深いものがあるような気がする。
そんな事を考えていると、がちゃりと背後のドアが開いた。
「あら浅見。もう起きてたのね」
にっこりと穏やかな笑顔をたたえてドアをくぐるのは、ルームメイトの碧。
「もう起きてたも何も。普段からこの時間に起きてるし、まだ寝てたら遅刻だろ……」
言い返してやると、彼女は「あら」と少し意外そうな顔をして。
「だって、浅見は良く寝るもの」
と笑った。
□ ■ □
夜。
「あら。こんな時間」
ぽつりと呟いて、読みかけのページに栞を置いた。
栞に描かれたハートのジャック。粗暴で怒りっぽい性格のカードをそっと挟み込んで、目覚まし時計のセットを確認する。
それから。足音を立てないよう、ベッドの傍らに立った。
部屋の両脇にあるベッド。
自分のと反対側にあるそこでは、すやすやと寝息を立ててルームメイトが眠っていた。
横から零れる髪を押さえて、そっと覗き込む。
時緒くんが「女顔」なんてからかうその顔は、寝顔になると一層あどけない。子供の頃と何も変わらない、かわいいとも感じる無邪気な寝顔。
「――なんて。言ったら浅見は怒っちゃうわね」
くすりと一人笑う。
「本当、浅見は良く寝るからそんなに大きく育っちゃうのよ?」
少しだけそんな文句を言う。
背が追い抜かれて、ああ、浅見は男の子なんだって思ったのは、一体いつだっただろう?
男には気をつけるんだぞ、って言われたのは?
負けないように強くなろう、って思ったのは?
きっと、言った本人は覚えていないだろう。
電気を消して、自分のベッドへ潜り込む。
静かな部屋で目を閉じる。
時々ああやって寝顔を見るのが楽しみだなんて。
彼の言った言葉を、今でもこうして大事にしているなんて。
これからも、内緒だ。