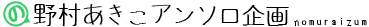春色甘味
しらゆき月華
時は大正。今年もこの地方に、桜が咲いた。
「乙彦~。乙彦、いる~?」
本格的な春を告げる桜が咲くと、人々の心ははやり浮き立つ。
そしてそれは、彼も同様――。
「はあいっ!はぁい姉さん!僕はここにいます!!」
・・・いや、もっとも彼の場合は、浮き立っているのは桜にではないようだ。
縁側から声をかけられた少年・乙彦は、元気よく手を振り、姉の前に姿を見せた。
庭掃除をしていたのだろう、松葉箒を握り締め、嬉しそうに駆け寄ってくる。
「ねーさん、僕に何か用事ですか?!」
・・・用事があったとして、そこまで嬉しそうにするものなのか。
彼を呼び立てた姉・神奈は、飼い犬のような弟の態度に内心苦笑した。
「暇なら、今から花見にでも行かない?通りに、新しい甘味処もできたらしいのよ」
そういうとさらに、乙彦の顔が輝いた。
「ね、ねーさん!そ、そそそれって・・・!僕とねーさんが今からデート・・・」
「あ、ただし乙彦には、して欲しい格好があるのよ」
「・・・え?」
少年は、大好きな姉との条件付きのデート(?)に、一瞬きょとんとした。
そして、数十分後。
玄関先には、ちょっと余所行きの格好をした姉と、綺麗に化粧まで施し、女装させられた弟がいた。
髪は短髪のままだが、元々ぱっちりとした目と愛らしい顔立ちゆえ、化粧をし女物の服を着せると・・・
たちまち少女・まるで神奈の妹のようになったのだ。
短髪に留めた髪飾りも、何ら不思議じゃないほどの愛らしさだった。
「・・・あの、ねーさん?僕は本当に嫌々着たんですが・・・これには一体何の意味があるんですか?」
「フッフッフ・・・よくぞ聞いてくれたわね、乙彦!実は今から行く甘味処は、女学生同士だと、なんと半額で飲み食いできるのよ!」
「の、飲み食いって・・・」
ピシャリと言い放った姉に、乙彦はげんなりした。
「本当なら、私も友達と行きたいところなんだけど・・・生憎誰も予定があいてなかったから。ああ、こういう時、可愛い顔の弟がいるって得よね♪」
「ちょ、ちょっとねーさん!僕はそんなことのために、生きてるんじゃないんですよ?!」
言い合いながらも、何だかんだで二人して、家を後にする。
甘味処に向かう道中、満開の桜が通りの景色を染めていた。
ひらり、ひらり。
あたたかい春風に吹かれて、花びらが枝から舞った。
そうして宙に落ちてからは、通りを行く人々の動きに合わせ、足元で舞う。
「はあ・・・やっぱりこの時期はいいわよねぇ~」
隣を歩く姉が、惚れ惚れとした声でつぶやいた。
「うん。毎年見てるけど、何回見ても綺麗だ・・・」
乙彦も同じように、宙を見上げて溜息を吐く。
愛しさの中に、どこか寂しさも感じさせる、春の風景。
ああ、この気持ちは――何かに、誰かへの想いにも、似ているような。
しみじみと浸っていると、ふと姉の声がした。
どうやら、目的の甘味処に着いたようだ。
店は花見時の午後だというのに、それほど客は多くなかった。
神奈と乙彦は同じものを注文し、神奈が目論見どおり、「女学生二人分」の代金を払った。
「あ、あの、ねーさん。お代・・・僕の分までありがとうございます」
「いーのいーの。そんなこと、乙彦は気にする必要なんかないのよ。・・・というより、あんたのその格好のおかげで、安く済んだんだから。お礼言うのは私の方よ」
申し訳なさそうに言う弟へ、神奈はぱたぱたと片手を振って答えた。
「・・・さ、お金浮いた分、食べれそうなら別の甘味も食べてみましょ。乙彦、甘いもの別に嫌いじゃなかったでしょ?」
「~~はい!僕、甘いものもねーさんも大好きですっっ!!」
大声で言った弟に対し、即座に姉の制裁が下ったのは、言うまでもなかった。
「まったくもう・・・今回は特に!場所を考えなさいよね乙彦・・・!」
「い、いてててて!ご、ごめんなさいねーさん・・・!!」
幸いなことに、店の店員は二人の注文の準備に追われ、聞こえていなかったようだ。
「はい、お待たせしました~」
思ったよりも人が少なかったため、甘味は、店外の長椅子に座って食べることにした。
店員は、神奈と乙彦の分の三色団子とほうじ茶を置くと、そのまま店内へと戻って行った。
「はあ~、三色団子なんて地味すぎる!とか言われるかもしれないけど、花見にはやっぱこれよねー!そしてこの団子の良し悪しで、店の格がわかるという・・・!」
「・・・そうなんですか?」
「いや、今のは持論よ?でも、私の中では絶対論」
楽しそうに語り、美味しそうに食べる姉。
その様子を横目に見ながら、乙彦も幸せな気持ちになった。
美しい桜が舞って、美味しいものがあって。
さらには大好きな人が隣にいて、笑っているなんて――。
桜と甘味を堪能した、帰り道。
乙彦はちょっとだけ、大好きな姉との距離を縮めて歩いた。
傍目には多分、二人の女学生か姉妹としてしか、映っていないだろうから。
「あの、ねーさん?」
「なあに」
「今日は、誘ってくれてありがとうございました」
ふいに立ち止まり、ぺこりと頭まで下げた弟。
その様子に、神奈は一瞬面食らった。
「・・・何か、そう面と向かって言われると、ちょっと恥ずかしいわね・・・。しかも、こんなに可愛い『妹』に」
「ちょ、ねーさん?!何でこんな時に、そんな台無しなこと言うんですかっ・・・!」
「えー?何が、台無しなのよ?」
にやりと悪戯っぽく笑った姉に、乙彦の動揺が一層増した。
真っ赤になった頬は、化粧のおかげでいつもより少し、目立たないのが救いだった。
春風が吹いて、また幾片か、桜が舞った。
それを合図にしたかのように、神奈が家へと走り出す。
そしてその後を、涙目になりつつ騒ぎつつ、乙彦が追いかけて行った。
春の、暖かさ。甘味の、甘さ。
そして、二人の姉弟の気持ちを表すとすれば・・・それぞれ、どんな温度なのだろう。どんな味なのだろう。
その答えがわかるのは――もう少し、先のことかもしれない。
(終)