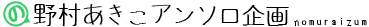■□■ HOME ■□■ K.K
「みんな集まってる~?」
僕の数歩前を行く女が懐かしい倉庫の扉を勢いよく開けた。
「さやちゃん!」
倉庫の中から聞こえた中園の声にドキンと胸が跳ねる。
別に自分が呼ばれたわけでもないのに・・・。
――― 不意打ちだっ!
思わず倉庫へ背を向け胸を押さえる。
透き通るような僕の白い肌は、きっと真っ赤だろう。
どうにも彼女のことは、恋愛対象でなくなった今でも、良い意味で少し苦手だ。
「お久しぶりっス、宮島女史!新郎と桜井くんがまだみたいですねぇ。」
「何言ってるのよ早乙女くんワガママ王子ならここに・・・って桜井あんた何やってのよ。」
扉に手を掛けたまま振り返った宮島が呆れたように、こちらを見ていた。
「何でもないっ!だいたいキミが入り口を塞いでるから僕はっ!」
仁王立ちで宮島を指差し盛大に自己主張するが、
「あーはいはい。とりあえず入んなさいよ。」
と人の話も聞かず、あの女はさっさと中に入っていく。
「くそっ・・・。」
思わず口から零れ落ちた悔しさに自分で顔をしかめる。
最初から気に食わない女だったが、こんな関係ではなかった気がする。
どちらかというと、僕の言動で振り回され大声を上げていたのは宮島の方だった。
世界を股にかける天才ピアニストと、そのマネージャーという関係になってから、彼女はすっかり僕の扱いが上手くなってしまった。至極不本意ではあるが。
「・・いくん・・・さくらいくん・・・桜井くん!!!」
いつの間にか目の前にいた中園江梨衣に叫ばれ、彼女特有の声圧に僕の前髪が宙へ舞った。
条件反射で耳を塞ぐが時既に遅し。
天才ピアニストの繊細な耳はキーンと耳鳴り地獄へ直行した。
「中、入らないの?」
中園はニコッと笑み、何事もなかったかのように倉庫の中を指差す。
「ッ・・・キミは本当、変わらないね。」
恨めしそうに言うが、彼女は「やだ~、照れちゃうじゃん」なんてはしゃいでいる。
「別に褒めたわけじゃないんだけど。」と苦笑する。
宮島なんかに言わせれば“珍しく優しく微笑んでる”んだろうが。仕方がない、彼女には勝てないのだ。
「ほらほら、時間ないし始めましょ。市堂くんは式の準備が忙しくて今日は来られないそうだから。」
よく通る宮島の声が寂れた倉庫に反響する。その言葉に中園はらしくもなく、少し静かに「そっか」と答えた。
中園の反応にベースの早乙女は困ったように笑い、中園兄が宮島に当日までの段取りを簡単に確認する。
呆けてしまっている中園に思わず声をかけた。
「キミは、大丈夫?」
問われた彼女は目を点にして、頭上に三つほど『?』が点滅している。
「ギターのこと・・・好きだったんだろう?」
努めて何でもないことのように、そう彼女に問う。今度は彼女の頭の上に『!』が点灯する。
このクルクル変わる彼女の表情が好きだ。ずっと・・・ずっと昔から。
「市堂くんのこと・・・大好きだよ、今も。“仲間として”ね!」
僕は息をのんだ。晴れやかに言う彼女の言葉に嘘はないだろう。強がりでもない。
その感情を知っている。僕も“そう”。
変わらず君のことが好きだけれど、意味合いは変化した。この約十年という歳月の中で。
こたえも返さず彼女を見つめていると、彼女は眉毛をハの字にして笑む。
「今日は七年ぶりに皆揃うなって思ってたから、少し残念に思ったけど。」
「そうだね。」と相槌を打って自分で驚く。
――― そうか・・・僕は残念に思っているのか・・・認めたくないけれど。
バンドを始めた時は、皆・・・特にギターの奴は邪魔で邪魔で仕方がなかったのに。
今、そのギター・市堂尊の結婚式で祝いのパフォーマンスライブをやろうというのだから、わからないものだ。
このために海外のスケジュールを丸々二ヶ月空けて、期間中は日本でのみ仕事を入れた。
スケジュールの都合をつけたのは、マネージャーである宮島清華の手腕であるが・・・
指示したのは僕であるし(言わなくても彼女は無理矢理都合をつけただろうが)、この僕がここまでしてやった。
市堂尊なんかのために。
結婚相手の浦川街子は、現在日本のトップ歌手まで上り詰めている。
角界の著名人が沢山、もちろん大物歌手なども出席するであろう式で、何故ほぼシロート集団がライブをしなければならないのかが、意味不明である。
そして、ギターの彼ではなく、あの浦川の要望とのことだ。
浦川と接点はないが、ないなりにも彼女の性格は想像に容易いし、この展開は完全にイレギュラーであると思う。
中園でさえも「驚いちゃった!」というくらいなので、あながち僕の見立ても外れていないだろう。
僕が少し変わったように、周りも少しずつ変わっていく。
これが成長というのだろうか?歩いた道を見つめ自分自身に問う。
軽く音あわせはしたが、ギターがいないためやれることも限られている。
結局のところ、ほとんどが雑談という破目になり、片付けをしながら僕のマネージャーは、また喧しく声をあげた。
「え~!早乙女くん、また彼女と別れたの!?」
「どーもボク、恋愛むいていないみたいなんですよねぇ。」
へらへらと笑うこの男もさっぱり変わらない。
自他共に認める中園江梨衣の親友であるが、おそらく恋愛対象として彼女を見ているのではないかと思う。
しかしながら、未だに“親友”という関係は変わらないようだ。
彼は優しいから、中園を大切に想うが故の“親友”という立場だろうが・・・。
昔、中園に告白をしてフラれている身としては、甘えに思えて気に入らない。
一足先に帰り支度を整えた中園兄が迎えに来た嫁の車で離脱する。
いつも最後まで残る中園も、母の誕生日だとかで兄と一緒に帰路についた。
「さてさて、桜井くん、宮島女史。僕達も帰りますか!」
「私車だし、桜井を家まで送って行かなきゃいけないから、もし良かったら早乙女くんも送ってくわよ。」
「あ、助かります~。」
「よいしょ。」と掛け声をかけて立ち上がる早乙女を、じっと眺めていると視線に気づいた当人が「どうしました?」と首を傾げた。
「キミにとって“中園江梨衣”はなんだ?」
疑問系を疑問系で返すと、早乙女は一瞬豆鉄砲をくらったような顔をする。その後ろで、宮島が息をのんでいるのが見えた。
当の早乙女はスッと笑うと「やだなぁ桜井くん。ただの親友っすよ。」と破顔。
――― なんて痛々しい顔で笑うんだ。
バンドを組みたての頃にも同じような問答をした。変わらない答えを僕に投げるが、言葉の重みがまるで違う。
「それならいいけど。そうでないのなら本気にならないと誰かに横から取られても知らないよ。」
少しの意地悪。しかし彼は動じる様子もなく口を開いた。
「桜井クン・・・・・・とかにですか?」
一瞬の鋭い眼光。
――― なんだ。そんな顔もまだ出来るんじゃないか。
思わずクスリと笑いを漏らすと彼は、きまりが悪い表情で顔を逸らした。
「“俺”は、ただ・・・エリーが幸せなら、それで良いんだ。」
「何よ・・・それ・・・。」
そう漏らしたのは、ガラにもなく置いていかれた形で大人しくしていた、宮島。
「・・・女史・・・?」
早乙女が目を見開く。宮島の瞳からはポロポロと水滴が零れ落ちた。
「手が届かなくなってからじゃ遅いの。誰かのモノになってからじゃ遅いのよ。“好きな人が幸せなら”なんて言葉、ちゃんと相手と向き合って闘ってから言いなさいよバカ!」
半ば叫ぶように言い切った宮島へデジャヴのようにハンカチを差し出す。
「それ以上、醜い顔になっても困る。」
「ちょっと!!それ、どういう意味よ!!だいたいね、あんたも敵に塩送ってどうするのよ!桜井だって、エリーのこと・・・。」
まだグズグズする宮島に溜息をついた。
「何を言っているんだい?キミは。」
一呼吸おいて、声のボリュームを少し上げた。
「僕は、中園江梨衣の“ただのファン”だ。」
瞬きもせずに、早乙女はこちらを見ている。宮島の瞳からは、まだ止まることなく涙が流れている。
泣く彼女が昔の記憶と重なる。
「・・・早乙女には、宮島のような思いはして欲しくない。」
ビクッと彼女の肩が震える。
「や、やめてよ!」
宮島が止めに入るが、早乙女は聞き流さなかったようで、宮島に視線を向けた。
「もしかして・・・女史も市堂くんのこと好きだった・・・?」
今、門出を迎えた仲間の名前を出す。
「ちっ、違うわよ!私はっ・・・。」
宮島は口をモゴモゴしてからキッと僕を睨みつけた。
「宮島女史?」
早乙女に呼ばれ、ハッと息をのむ。
「わ、私、車とってくるから。」
バッと立ち上がると、止める間もなく外へ走り出してしまった。
宮島の背中を見送り、僕は早乙女に「中園兄だ。」と伝える。
「ヒロさん・・・?」
彼の結婚が決まった時の彼女の姿は今でも覚えている。
彼女が僕のマネージャーになってから一年を迎えようとしていた辺りだった。
僕のマネージャーは、とても強い女だ。
もともと僕には、性格上、仕事でも敵が多かった。
それは、否応なくマネージャーである彼女にも降り掛かる。
彼女が来る前までのマネージャーは、皆、僕とあわずに辞めるか、周りからの攻撃に耐えられず辞めていくか、はたまた両方か。
いずれにしろ早ければ一ヶ月・・・長くても半年以内には必ず去って行く。
それを彼女は一年近く持ち前の根性でいなしてきた。
相変わらず、小言は多いし喧しいが、明るく誰とでもすぐ打ち解けるので人付き合いも良好。
弱音を吐くくらいなら「今に見てなさい!」などと言って自分自身に鞭を打つ。
だから、それまで僕は、弱った彼女を見たことがなかった。
否、正直、あまり他人に興味がないので気がつかなかっただけかもしれないが・・・。
中園比呂衣の結婚の報が入ったその日、夕食を共にしていた彼女が急にポロポロと泣き出した。
意味がわからず、そんな彼女を迷惑だと思ったが・・・。
強い筈の彼女が、か細い声で「ずっと、好きだった。」と漏らす。
それだけで充分だった。
唇を噛み締める彼女を、ただ興味深げに眺め
「結局、最後まで言えなかったな・・・」
また小さく漏らした声を聞きながら、スーツのポケットに手を入れハンカチを取り出す。
「キミも、女の子だったんだね。」
普段の彼女なら激昂するであろう率直な感想を述べながら、それを手渡した。
そのまま放っておくことも出来ず、僕のマンションに連れて帰った。
彼女は朝方まで泣き続け、やっと泣き疲れて眠った宮島をベットに運び、自分は仕事までソファーで仮眠をとる。
そんな日でさえも時間通りに起きた彼女は、僕に普段は下がらない頭を下げながら一度帰宅する準備を始めた。
――― 仕事をする気か?
思わず漏れた溜息。
酷い顔だった彼女に三日間の強制休日を与えたのは、もう二年前の話だ。
「宮島は、想いを伝えられなかったことを後悔している。」
早乙女はまだ僕から視線を外さない。
「中園の隣に立っているのは、いつだってキミなのに・・・中園が幸せであれば良いなんて、そんなの・・・。」
何か言おうと彼が小さく息を吸ったところで、畳み掛ける様に続けた。
「君が幸せにすればいいだけの話じゃないか。」
早乙女の口からは声が聞こえない。
代わりに聞こえたのは、呼吸音。
「はぁ・・・カンタンに言ってくれるね・・・。」
伝染したように、僕も吐息が零れる。
まだ煮え切らない言葉に、暫し目を瞑った。
遠くから耳慣れた車のエンジン音が近づいてくる。
宮島が倉庫の前まで戻ったらしいが、本人が中へ入ってくる気配はない。先ほどのことを気にしているのだろう。
あの状態で待たせておくのも、些か可哀想か・・・。
――― 僕が、宮島の心配か。
「随分、毒されたものだ。」
独りごちて目を開ける。
かすかに僕の声が届いた早乙女に「何?」と尋ねられたが、「宮島が来たようだ、外に出よう。」と受け流す。
昔であれば、宮島を待たせておくなんてこと、何でもないことだった。
早乙女に気がつかれただろうか?とも思ったが、どうでも良いことだ。
どの道、観察眼に優れた彼も、今は人のことまで気が回らない。
先に歩き出した僕の背に「桜井」と声がかかり、立ち止まって振り返れば、真剣な早乙女の双眸に動きを絡めとられる。
それ以上の身動きはせずに、彼の言葉を待った。
「桜井は・・・本当にもうエリーのこと好きじゃないのか?」
――― 馬鹿だな。
「僕がライバルに塩を送るような“お人好し”に見えるのかい?」
得意げに言うと、彼も破顔する。
「言ったろ?僕は中園江梨衣の“ただのファン”だ。それに・・・。」
するりと口から出そうになったセリフを噛み殺す。
しかし、ペースを少し取り戻せば、それを見逃すような早乙女ではない。
「それに?」
――― 言うつもりはなかったんだけどね。
「・・・。他に、好意を持っている人がいる。」
失礼なほど、わかりやすく驚いた彼は、金魚のように口をパクパクさせた。
「中園の時のようにドキドキはしたりしないけど。でも、傍にいるのが当たり前のように落ち着くんだ。・・・中園に負けず劣らずのじゃじゃ馬だけどね。」
――― なんで、あんな女を好きになったりしたのか、自分でも謎だ。でもまぁ・・・
「“理屈なんて、どうでも良い”なんて、らしくないことを考える程度には本気かな。」
「リクツなんて、どうでもいい・・・ね。」
復唱するように早乙女が呟く。瞬きをした彼の瞳には強い光が映った。
それを確認して、僕は、また踵を返す。それを追うように早乙女の足音が聞こえた。
「桜井くん、桜井くんの好きな人って、どんな関係の方なんですか?」
いつもの調子を取り戻しつつある彼は、興味深げに尻尾を振ってくる。
「キミには関係ない。」
「桜井くんばっかりズルイじゃないですか。」
彼の言葉に足を止めると、小走りについてきた彼が僕にぶつかった。
「うわっ。ちょ、桜井君、急に止まらないでくださいよ!この早乙女藤馬、急には止まれません!」
「・・・捨てでいい。」
「はい?」
「呼び捨てで構わない。」
意味を量りかねたらしい彼が首を傾げた。
「さっき、呼び捨ての方が呼びやすそうだったから。」
そういうと彼は「あれは・・・。」とバツの悪い顔をする。
「どちらもキミであると心得ているけれど、あっちの方がより素のキミだ・・・と僕は解釈している。」
呼び捨てになったり、“僕”が“俺”になったり、どちらも彼であるが感情的になるとより本質に近くなる。
とても器用そうに見える彼だが、誰よりも不器用だ。
「行くよ。」と倉庫の扉を開けると、宮島が「遅~い!」と声をあげる。
「お待たせしてすみません女史~~~!!」
何事もなかったかのように、早乙女は宮島に絡む。
その光景に少しムッとするが、それに気がつかない宮島から「あんた達、早く乗んなさい。」と片付けられる。
「僕、やっぱり歩いて帰りますよ。鍵も閉めておきますから、お構いなく、どーぞ。」
やはりにっこり笑った早乙女は、宮島に敬礼する。
「乗っていけばいいのに~。」なんてブーブー言う宮島に構わず、僕は助手席に乗り込む。
開いていた窓から、早乙女が「耳をかしてください。」と手招きをした。
言われるがまま彼へ顔を近づけると、そっと耳打ちをされた。
「エリーのこと、がんばってみようと思います。」
そして続ける。
「僕、今日はエンリョしますんで・・・宮島清華も手強いと思いますが、ご武運を!」
予想もしていなかった言葉に息をのむ。
宮島が車を出すと、ルームミラーに手を振っている早乙女の姿。
僕は顔が真っ赤になり、心臓がバクバクしている。
助手席の異常に気がついたのか、運転席の彼女から「どうしたの?」と声をかけられる。
「何でもない。」と返せば、すぐさま「なによ、心配してあげたのに」と膨れっ面。
そんな彼女に構わず、僕は、右手でこめかみを押さえ今日一番の深い溜息をついた。
「まったく・・・くえない男だ。」
END